
今回は、北海道の先住民族「アイヌ民族」についてご紹介します。
豊かな自然に囲まれた北海道の大地で、アイヌの人々は長い年月をかけて独自の文化を築き上げてきました。
彼らの暮らしは自然と深く結びついていて、動植物や道具のひとつひとつに神が宿ると信じられていたのです。
本記事では、アイヌ民族の生活や自然への信仰、ユーカラ・カムイユカラといった口承文芸、そして現在も訪れることができるコタン(集落)についてご紹介します。観光だけでなく、文化や歴史を深く知るきっかけとして、ぜひ最後までお読みください。
なお、アイヌ文化を訪ねる旅に便利な宿泊施設もあわせてご紹介しますね。
アイヌ民族の暮らし~コタンに暮らす人々と今に伝わる文化
その昔、北海道は「蝦夷地(エゾチ)」と呼ばれていました。
「エゾ」とは、もともとアイヌ民族を指す言葉で、史料上で「アイヌ」と記されるようになったのは鎌倉時代以降とされています。
アイヌ民族は、北海道を中心に、樺太(サハリン)や千島列島、カムチャッカ半島などにも暮らしていた先住民族です。
また、日本列島の各地、特に東北地方にもアイヌと関係のある部族がいたと考えられています。
アイヌ民族は、日本語と系統の異なる独自の言語をもっていました。
自然界すべての物に魂が宿るという「精神文化」を大切にして暮らしていたのです。
その歴史や文化は、今の私たちが住むこの土地を深く理解するための貴重な手がかりとなります。
アイヌの暮らしと自然との共生
アイヌの人々は、木や草など身の回りにある自然の恵みを使って暮らしていました。
-
住まいは「チセ」
草木を編んだ家で、中心には暖炉(アペ)がありました。
火は生活の中心であり、神聖な存在でもありました。 -
衣服
「アットゥシ」と呼ばれる織物や、動物の皮で作られました。
魔除けを意味する刺繍模様が施されていたのも特徴です。 -
食生活
季節に合わせた自然の恵みを大切にしていました。
サケや山菜、木の実、シカ肉などを取り入れた健康的なもの。汁物「オハウ」は日常的な料理のひとつです。
狩猟と採集の知恵
アイヌの暮らしは、自然からの恵みをいただく「狩猟」「漁労」「採集」によって支えられていました。
彼らの生活の中心は狩猟でした。
山で熊・鹿、川で鮭を獲り生活していたのです。
全ての自然に神がいると信じ、自分たちも自然の一部として生きてきました。
-
狩猟では、弓矢や毒矢を使ってエゾシカやヒグマを仕留めました。
獲物への感謝を忘れず、無駄なく使い尽くす知恵があったのです。 -
特にサケ漁は重要で、川を遡上するサケを木製の仕掛けで捕らえていました。
今のように冷蔵庫などはありません。
干物や燻製にして保存していました。
冬は凍らして今のルイベのように食べたこともあったようです。 -
春から秋にかけては山菜や木の実を採集していました。
自然と対話するように、食べごろや採取の時期を見極めていたといいます。
カムイ(神々)と信仰の世界
アイヌの人々は、あらゆるものに「カムイ(神)」が宿ると考えていました。
カムイはあらゆるところに存在していて、いつも自分たちを見守っていると考えていました。
火、水、道具など、すべてのものが神の姿をしてこの世に来ているとされていました。
動物、植物などは、肉や毛皮などを土産として人間の世界にやってきます。
紙には、山の神「キムンカムイ(ヒグマ)」、海の神「レプンカムイ(シャチ)」、家の火を司る「アペフチカムイ」などがいます。
特に有名なのが「イヨマンテ(熊送り)」という儀式です。
クマを神の化身として大切に育て、その霊を神の国へ送り返す神聖な行事です。
春先に子熊を捕獲しその子グマを大事に育てます。
後1,2年育てた後に盛大な儀式を執り行い、その魂をカムイモシリ(神々の世界)に送り帰すのです。
イヨマンテのほかにも、その年最初に採れた鮭をカムイに捧げる儀式「アシリチェプノミ」
祖先を供養する儀式「イチャルパ」などの儀式がありました。
イヨマンテなどは、見学できる施設もありますので一度は足を運びたいですね。
アイヌ民族の口承文芸 ・語り継がれる物語〜ユーカラとカムイユカラ〜
アイヌ民族が育んできた文化の一つに、さまざまな「口承文芸(こうしょうぶんげい)」があります。
これは、文字で書かれたものを読むのではなく、語り手が話す物語を耳で聴いて受け継いでいく伝承形式です。
文字で書かれた話と違って、同じ話でも語り手によって違ってきます。
また、同じ語り手でもその場やその時によって、語り方や表現などに違いが出てきます。
その人その時ならではの味わいが含まれるのも特徴です。
アイヌの言葉と言語の特徴
アイヌ民族には独自の文字がなかったため、文化や歴史、信仰などはすべて「語り」によって次の世代へと伝えられてきました。
アイヌ語は、ア・イ・ウ・エ・オの5つの母音を持ち、日本語と似た語順(例:「〜が」「〜を」「〜する」)を使うこともあります。
ただし、ガ・ギ・グなどの濁音が存在せず、文法や発音には日本語と異なる特徴が多く見られます。
かつては口頭でのみ使われてきた言葉が、明治以降の近代化の過程で、だんだんと失われていきました。
大正時代ころから、研究でローマ字やひらがな、カタカナなどが用いて書かれるようになりました。
従来のカタカナにはない文字(ト゚、ㇰ、ㇷ゚、ㇵなど)も使いながら工夫して表記されています。
2009(平成21)年、ユネスコによって消滅の危機にある言語と位置づけられています。
アイヌ民族の「口頭文芸」
アイヌの口頭文芸には、メロディーを伴って謡うように語るものもあれば、それよりは比較的単調に、話し言葉のようにして語るなど、さまざまな語り方をするものがあります。
アイヌの口承文芸は、一般的に以下の3つに分類されます。
・英雄叙事詩(ユーカラ)
・神謡(カムイユカラ、オイナ)
・散文説話(昔話など)
その物語の中の一つが、良く聞く「ユーカラ物語」です。
ユーカラ物語は、地方によってはサコロペ、ハウキなどと呼ばれていました。
少年の英雄が主人公となる内容が多くあったので「英雄叙事詩」とも言われてきました。
この物語は、独特のリズムと旋律に乗せて、親から子へ、子から孫へと代々口頭で伝承されてきました。
神謡はカムイユカラ、オイナなどと呼ばれています。
短いメロディーを繰り返しながら物語の言葉をのせるようにして語られます。
さまざまなカムイが、カムイの世界や人間の世界で体験した身の上を語るものが多くみられます。
こうした神謡を通して、自然界に対する敬意や、共存の知恵、人間としての在り方などが語られてきました。
それぞれの物語ごとに、おおよそ決まったメロディーがあります。
語るときには決まった言葉が繰り返し挿入されることが特徴です。
その言葉はそれぞれの物語によってだいたい決まっています。
これらの言葉は、神謡の主人公であるカムイの鳴き声などからきているものが多いという説もありますが、言葉の意味がよくわからない場合もあります。
これらの物語は、明治になってから書き物になっています。
アイヌ民族の居住地~アイヌ文化を学べる施設紹介
北海道の地名にはアイヌ語をもとに名付けられた名前がたくさんあります。
その地名をみると札幌市は、「乾いた広いところ」または「乾いた大きな川」を意味する「サッ・ポロ・ペッ」と呼ばれていたように、川・沼・山・湖などを意味した地名がたくさんあります。
その名前の意味を考えるとアイヌ民族がその地をどのように感じ、どのような所だったのかうかがい知ることができるのです。
北海道が蝦夷地(エゾチ)と呼ばれたその昔、北海道の各地にアイヌ民族は点在して暮らしていました。
アイヌ民族は、自分たちの住む土地、北海道の事を「アイヌモシリ」と呼んでいました。
「アイヌモシリ」とは、自分たちの島という意味を持っているのです。
まさにアイヌ民族にとっては、自由の天地でした。
アイヌ民族は、水が豊富で鮭や魚ががたくさん捕れる河川や河口の近く。
魚がたくさん棲む湖のほとりにコタンと呼ばれる部落を作り住んでいました。
コタンには数軒の家(チセ)がありました。
チセは、アイヌの人々の伝統的な家屋です。
釘などの人工物は使わず周辺の山林から得られる木や草といった自然物で作られています。
掘立柱を地面に直に立て、柱と梁を組んで屋根を支えた寄棟の掘立柱建物です。
屋根と壁をクマ笹で葺いたり、樹皮で屋根や壁を葺くなど地方によって特徴があります。
部屋の中央には炉があります。
その上座には、カムイプヤㇻ(神窓)という神が出入りする神聖な窓が付いています。
神から授けられた肉を運び込んだり、儀式の祭具を出し入れしたりするのに使われていました。
家の周辺部には、冬のイオマンテで天界に送るためのヘペレ(小熊)を飼うヘペレセッ(檻)や、食料を保存するプ(高倉)、アシンル(便所)なども建てられていました。
そんなコタンで鮭などをとり生活していたのです。
今でこそ鮭の捕獲量もだんだんと少なくなっていますが、昔は鮭の間に棒を立てても倒れないほどの鮭が遡上していました。
マレクという鉤銛(かぎもり)ややなを仕掛けるなどいろいろな方法で捕獲していました。
また近くに獣たちがたくさん棲む山があれば、トリカブトの毒を塗った矢で鹿なども捕獲したのです。
しかしその〝アイヌモシリ〟も10世紀を過ぎると次第に破壊され始めました。
アイヌ民族と神々とのつながりが途絶えたわけではなく、自然の変化や資源の減少が生活を脅かしたのです。
今でも、北海道にあった大きなアイヌコタンの後には、博物館やその伝統を伝えるためのコタンがあります。
その中から古い記録から伝統的な踊りを復活させようと取り組む人たちや、新しいアイヌ音楽を創造する人たちも増えています。
道内に今もある、アイヌ民族が暮らすアイヌ部落をご紹介します。
川村カ子ト(カネト)アイヌ記念館~近文コタン
石狩川流域一帯に転々と住んでいたアイヌ民族が、都市計画によって市の西地区に集められて出来たのが近文コタンです。
アイヌの人たちは、近文(チカブミ)を「チカプニ」鳥のいるところと呼んでいました。
鹿さえも簡単につかんで飛ぶことができた大きな鳥が、嵐山の石狩川沿いの崖にいたという伝承があり、そこから石狩川右岸は広くチカプニと呼ばれるようになったそうです。
今は、その場所に川村カ子トアイヌ記念館があります。
明治期から大正・昭和初期にかけて、旭川に天才と呼ぶにふさわしい鉄道測量技手がいました。
その人の名は、川村カ子ト(カネト)で、旭川の近文で生まれ育ったアイヌの酋長です。
少年の頃見た蒸気機関車に魅せられたカ子トは、学校を卒業すると同時に測量人夫へとなり、そして測量技手の名手に登りつめていきました。
その身体能力、頭脳、リーダーシップ力は誰もが認めるところとなり、宗谷本線や根室本線をはじめとする鉄道施設の測量の先頭に立ちました。
北海道に敷設された鉄道の測量の大半は、カ子トをリーダーとするチームによって成し遂げられたのです。
しかし晩年は目を患って退職しました。
その後、全ての私財を投じ、アイヌの酋長としてアイヌ文化を後世に伝えるための記念館を設立したのです。
大正5年(1916年)に作った日本最古で唯一の私立のアイヌ資料館が誕生しました。
それが川村カ子トアイヌ記念館です。
アイヌの文化や習慣を伝える生活用具など貴重な資料が数多く展示されています。
また、測量技師時代の測量機材や資料も展示しており、川村カ子ト氏が測量技師として多くの業績を残したことを垣間見ることができます。
屋外には、ササを葺いたチセ(アイヌ語で家の意味)があり、チセでのアイヌの生活が体感できます。
また、敷地内にはアイヌ民芸品を扱う売店も設置されています。
川村カネト酋長は、昭和52年(1977年)1月老衰のため、生まれ故郷である旭川市で83歳の生涯を終えました。
川村カ子トアイヌ記念館見学案内
所在地 旭川市北門町11丁目
TEL 0166-51-2461
FAX 0166-52-6518
駐車場 あり
営業時間 9:00〜17:00
定休日 5月~11月:無休/12月~4月:火曜日
入館料
大 人 800円(600円)
大学生 600円(500円)
中高生 500円(400円)
小学生 300円(250円)
未就学 無料
阿寒湖アイヌコタン
阿寒湖アイヌコタンは、現在でも約120名のアイヌ民族の皆さんが暮らしています。
阿寒湖アイヌコタンは、(1959年)前田一歩園3代目園主・前田光子氏がアイヌの生活を守るために土地を提供したことからその歴史が始まりました。
伝統文化を受け継ぐアイヌ民族のみんなが、受け継がれてきたものを大切にしながら、現代的なものの見方や技術を取り入れ「伝統と革新」を体現しながら店を構えています。
我が国の先住民族であるアイヌ民族が大切に守り受け継いできたアイヌ文化の精神性を感じられる場所です。
★阿寒湖アイヌシアター「イコㇿ」
「イコㇿ」は、伝統あるアイヌの文化を肌で体感できるアイヌ文化専用屋内劇場です。
ユネスコ世界無形文化遺産に指定された「アイヌ古式舞踊」。
映像や現代舞踊の演出を加えた「ロストカムイ」などの演目を鑑賞できます。
アイヌが語り継いできた「イコロ(宝)」が、アイヌの精神を体現した伝統の歌と踊りで迫力満点に表現されます。
阿寒湖アイヌシアター「イコㇿ」見学
料金
阿寒ユーカラ ロストカムイ
大人(中学生以上)2,200円 / 小学生700円
アイヌ古式舞踊
大人(中学生以上)1,500円 / 小学生700円
TEL:0154-67-2727
座席数 332席
★伝統・創造「オンネチセ」
「オンネチセ」は、伝統を守り新たなものづくりを続ける阿寒湖アイヌのアートギャラリーです。
阿寒湖アイヌの新旧の作品を収蔵しています。
アイヌ語でオンネは「大きな・完成に近づいた」、チセは「家」を意味しています。
「オンネチセ」は、伝統を守りつつ新たな文化創造を重ね続け、“完成に近づけたい”という想いのもと誕生しました。
ギャラリーでは、阿寒湖温泉の地で収集された伝統工芸品が見れます。
★アートギャラリー「オンネチセ」
料金
大人(中学生以上)500円 / 小学生250円
時間
6~9月 毎日
5月・10月 土日祝のみ
11月~4月 休館
開館時間 10:00-16:30
TEL:0154-67-2727
アイヌ民族の文化や歴史、そしてコタンという場所で今も受け継がれている暮らしかたは、私たちに多くの学びを与えてくれます。
観光の一環としても、現地を訪れ、アイヌの心にふれる体験をしてみてはいかがでしょうか。
アイヌ民族施設見学におすすめのホテル
北海道内の各地に点在するアイヌコタン。
奥が深いので見学も時間をかけてゆっくりしたいですね!
そんな時に便利な、アイヌコタン近くのホテルをご紹介します。
旭川キャピタルホテル
「旭川キャピタルホテル」は、近文コタンから一番近いホテルです。
ホテル自体は多少古いホテルですが、リーズナブルなプランが人気です。
フロントなどの対応も素晴らしく、駐車料金も普通車なら無料。
予約が取りづらいと隠れた噂のホテルです。
人気のプランは、こちらからご覧ください。
あかん遊久の里 鶴雅
「阿寒湖アイヌコタン」を見学するのには、「あかん遊久の里鶴雅」がおすすめです。
お部屋・食事・温泉どれを見ても高ポイントで大変人気のホテルです。
阿寒湖を見ながらくつろげるお部屋の様子は、こちらからご覧ください。
旅のだいご味が詰まったような温泉が楽しめます。
阿寒湖のほとりのお散歩はもちろん、ちょっと足を延ばしてオンネトーや摩周湖にも便利。
道東観光の拠点にぴったりなホテルです。
アイヌ民族のまとめ
北海道が蝦夷地と呼ばれるもっと以前から、この大地にはアイヌ民族が暮らしていました。
あらゆるものに「カムイ(神)」が宿ると考え、豊かな自然の中で自然の恵みを感謝しながら生きていました。
山で熊・鹿、川で鮭を獲り生活していたのです。
アイヌは言葉を持ちませんので口頭文芸と言われる、ユーカラやカムイユカラ、オイナなどメロディーを伴って謡うように語ったり話し言葉のようにして語りました。
さまざまな語りを独特のリズムと旋律に乗せて、親から子へ、子から孫へと代々口頭で伝承したのです。
アイヌ民族の暮らしや信仰をみると、「自然を恐れず、敬いながら共に生きる」という深い知恵が感じられます。
現代社会では失われつつある感覚ですが、アイヌの世界観には、これからの時代にこそ必要なヒントがたくさん詰まっています。
今でも、北海道にはアイヌ民族が暮らすアイヌがあります。
時間が許せば近文コタン・阿寒湖アイヌコタンなど今でもアイヌが暮らし、アイヌの生活を垣間見れるコタンを訪ねてアイヌ文化に触れる旅も楽しみたいですね。
今回は、アイヌ民族の文化や歴史、そしてコタンという場所で今も受け継がれている暮らしかた。
独特のリズムと旋律に乗せて、親から子へ、子から孫へと代々口頭で伝承してきた口頭文芸。
今も、アイヌ民族が暮らすコタンをご紹介しました。
チセなどの建物、展示されている生活用品。
昔を再現するアイヌの踊りなどその土地に行かなければ、見ること感じることができないものもたくさんあります。
北海道を訪れた時には、ぜひ足を運んでアイヌ民族の歴史を見てください。
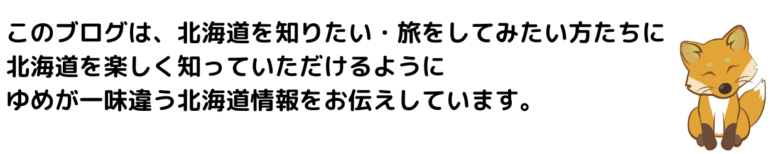





コメント