
北海道の地名
北海道の地名は、 アイヌの風習・生活が地名の由来になっております。
北海道の市町村の地名で、およそ8が割がアイヌ語をもとにしてつけたと言われます。
現在では、そのほとんどが漢字で書き表されていますが、アイヌ語にそのように読める漢字を無理に当てはめたのです。
ですから見た瞬間どう読んだら良いのか、悩んでしまう地名が数多くあります。
北海道に暮らしている人は、町の名前が昔アイヌの人たちが使っていた地名を、もとになって付けられていることを知っていと思います。
地名で昔の生活が想像できる
北海道の地図を眺めていると、「内」や「別」がつく地名が多いことに気がつきます。
実は、これらはアイヌ語で「川」を表す言葉「ナイ」「ペッ」に由来します。
アイヌの人々は、川で鮭をとり川と密接にかかわる暮らしをしていたので、川にまつわる地名が多いと考えられます。
アイヌの人たちが付けた地名には、その土地などの、地形や特徴、昔そこでよく行われたことなどを地名とし、その地名をもとにしているのです。
札幌市も、アイヌ語のサッポロペッ「乾いた大きな川」にそう読めそうな漢字を探し、札幌という字をあてはめたのです。
このように、アイヌ語地名を読み解くと付けた当時の人たちの生活が垣間見えるのでございます。
狩猟生活をしていたアイヌ民族
アイヌ語の地名は狩猟生活であった彼らの生活と、深く結びついていることがわかります。
アイヌの人々は、地形や植物、動物の習性を熟知していました。
暖かい時期は山菜を採り、秋にはサケ漁をし冬には、弓矢や罠を用いたり、海や川に追い込んだりして、エゾシカやウサギ、キツネ、タヌキなどの動物を狩りました。
トリカブトからつくった強力な矢毒で、ヒグマも仕留めることができたのです。
アイヌ語の地名は、アイヌ民族が使っていた言葉・その歴史・はぐくんできた文化を身近に伝えるもので、関心を持つ人もたくさんいます。
でも現在は、自然の地形も変わり社会的様式も大きく変化しています。
アイヌ民族が自然と関わりながら付けた名前の意味を、正確に証明するのは難しいでしょう。
元々、ごく狭い範囲につけて使っていた地名が、ひとつの大きな町やもっ地方を表すようになった地名が多くあり、地名の元々の由来がわからなくなった様なところもたくさんあります。
その意味からも、アイヌ語の地名は歴史的に見てもとても重要な文化財ということができるでしょう。

分かるかな?北海道の地名

ゆめ
難しい北海道の地名を集めてみました。
いくつ読めますか?
| 地名 | 読み方 | アイヌ語 | アイヌ語の意味 |
| 長万部 | おしゃまんべ | オシャマンベ | 河口にカレイがいるところ |
| 花畔 | ばんなぐろ | パナウンクㇽ・ヤソッケ | 花畔の場所。川下の衆の漁場 に由来した地名です。 |
| 厚岸 | あっけし | アッケ・ウㇱ | オヒョウの木の皮を剥ぐところ |
| 興部 | おこっぺ | オウコッペ | 川尻の合流しているところ |
| 忍路 | おしょろ | ウショロ | 入り江 |
| 相内 | あいのない | アイヌオナイ | 人の多い沢 |
| 音威子府 | おといねっぷ | オトイネプ | 濁りたる泥川 |
| 丸瀬布 | まるせっぷ | マウレセプ | 三つに分かれている広いところ |
| 訓子府 | くんねっぷ | クンネプ | 黒いところ、やち川にして水黒し |
| 渚滑 | しょこつ | ソー・コッ | 滝つぼ |
| 歌棄 | うたすつ | オタ・シュツ | 浜の草原が尽きる砂原に掛かる辺り |
| 稀府 | まれっぷ | イマリマレㇷ゚ | イチゴがあるところ |
| 弟子屈 | てしかが | テシカ・ガ | 岩磐の上 |
| 国縫 | くんぬい | クンネ・ナイ | 黒い川 |
| 鳧舞 | けりまい | ケリマㇷ゚ | 履き物焼くところ |
| 雄武 | おうむ | オムイ | 河口が塞がる |
| 和寒 | わっさむ | ワットサム | ニレの木の傍ら |
| 椴法華 | とどほっけ | トトポケ | 岬の陰 |
| 妹背牛 | もせうし | モセウシ | イラ草の多いところ |
| 簾舞 | みすまい | ニセイオマップ | 峡谷にある川 |
| 別寒辺牛 | べかんべうし | ペカンペ・ウㇱ | ヒシのあるところ |
| 富岸 | とんけし | トー・ケㇱ | 沼の端 |
| 秩父別 | ちっぷべつ | チックシベツ | 通路のある川 |
| 大楽毛 | おたのしけ | オタ・ノシケ | 砂浜の中央 |
| 幣舞 | ぬさまい | ヌサ・オ・マイ | 幣場の・ある・ところ |

ゆめ
いかがでしたか?
いくつの地名が読めたでしょうか?
北海道に住んでいても、なかなか読めない地名もありますので、本当に難しいですね!!
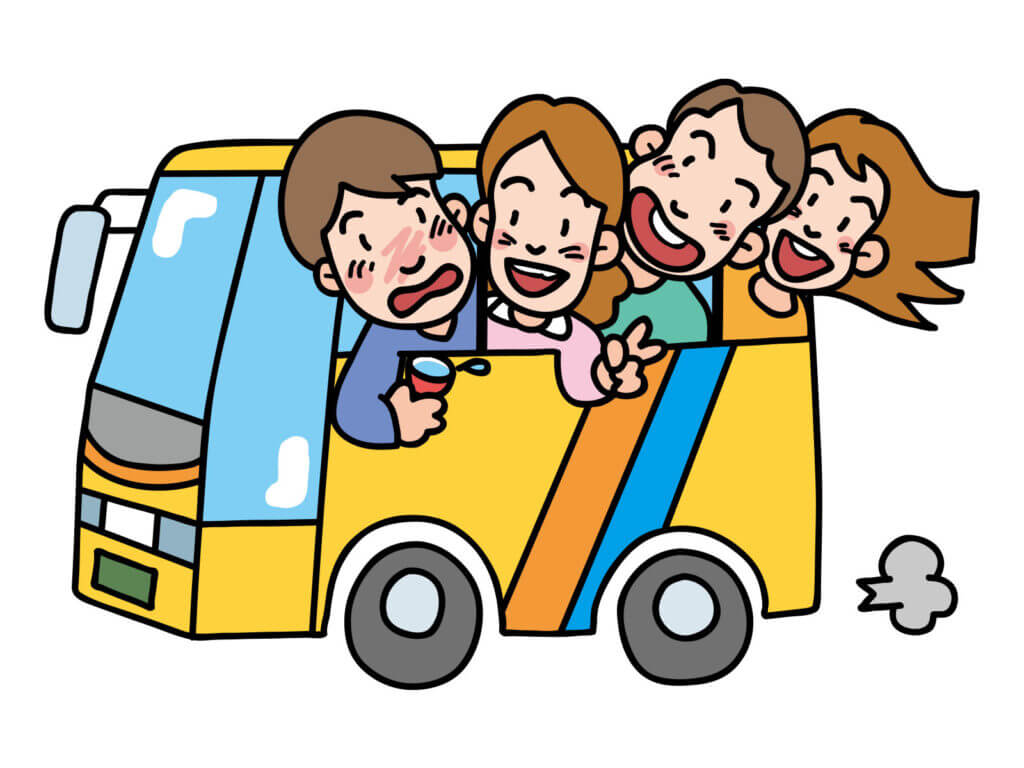
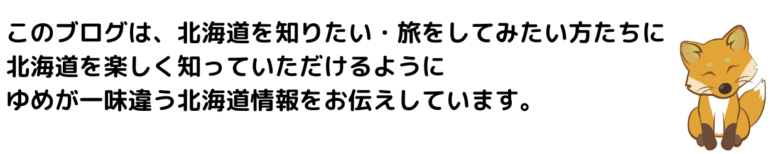



コメント