
北海道に住む動物たちからのお願い
北海道を旅するとき、草むらからひょっこりキツネが顔を出したり。
エゾ鹿が群れで道路を横断、エゾリスが木の上になど野生動物と遭遇する場面が良くあります。
知床半島では、ヒグマまで見ることがありますから大自然とともに動物たちもそこで暮らしています。
キツネとかリスを見ると可愛くて、ついつい何か食べさせてあげたいなあなんて考える人も多いでしょう。
でもその行為は動物のためにはなりません。
「餌付け」は、しないでください!!
人からエサをもらったり、ごみの放置などで人間の食べ物の味を覚えた野生動物は、自分でエサをとることをしなくなってしまいます。
その味に執着して、人に近づく危険なクマになってしまいます。
実際、近年ヒグマが住宅地で人を襲ってけが人が出たこともあります。
このようになると駆除の対象になってしまいますので、動物自体も可哀そうなことになります。
また、人からエサをもらうために道路に出て、自動車に轢かれるなどの交通事故にも遭いやすくなります。
動物たちのためにも、野生動物にエサは与えないでください!!
北海道に住む動物
北海道には、可愛い野生動物がたくさんいます。
北海道にしかいない動物をご紹介します。
きたきつね

大きな耳に太いしっぽ、最近では、北海道日本ハムファイターズのきつねダンスで一躍人気者になりましたね。
私の家にも冬の間は、明け方近くにキツネが来ます。
雪に残る足跡が4本足なのに真っ直ぐなのできつねだとわかります。
キツネは情の深い動物で、春に子供を3匹から6匹産み夏の終わり小ギツネが独立していくまで、実に良く面倒を見ます。
初夏には、親子連れ立って歩く姿をよく見かけます。
きたきつねは、頭の良い動物で冬の足跡も、巣の近くに行くと乱れたり、後戻りして追う者の目をくらまします。
巣には、いくつもの出入り口を作り、一方がふさがれてもほかの出口から逃げれるようにしているのです。
昔からキツネは人をだますとか化かされるとかいわれますが、これはキツネの頭の良さから来たのではないでしょうか?
野鼠やウサギなどの餌をとる時には、自分が傷ついているように倒れたり転げまわったりしれ、相手が安心して近づいてきたところを仕留めるというずる賢さがあります。
※ただ可愛いだけでなくエキノコックスを媒介しますので、ふんなど触らないように注意が必要です。
エゾリス

北海道平地では、亜高山帯までの森林で見られます。
体長約25cm、体重約350gほどの小型の哺乳類で、毛の色は、夏は茶冬は灰色になります。
春は朝から活動し、夏は日が出たら暗くなるまで活発に、秋は昼間だけ、冬は朝だけ活動することが多いようです。
冬眠はしないで真冬でも活動するため、林を走るリスの姿もよく見られます。
エゾリスは、秋になると餌が少なくなる冬のために、木の実を集めて地面に埋めておきます。
雪が降っても根雪を50~60cmも掘って潜り、自分で貯蔵してある餌を探すことができます。
自分の体重の3分の1の重さの木の実を、口にの中に一杯入れて運ぶことができます。
口いっぱいに木の実をほおばるエゾリスは、とっても愛くるしくてかわいいですね。
シマエナガ

まあるくて、コロコロして真っ白・数年前からとっても人気の鳥シマエナガです。
シマエナガは、日本では北海道にしか棲んでいない鳥で「雪の妖精」ともいわれます。
体長は、10㎝から14㎝重さ10gとスズメより小柄な鳥で餌を探したり、天敵(カラス・蛇など)から身を守るため飛び回るので見つけるのが難しいです。
5羽から10羽で群れで生活しているのでぜひ見つけてみたい鳥ですね。
丹頂鶴

北海道東部の湿原を中心に分布している鳥です。
全長140cm、体重10kg前後で、国内の野鳥では最も大型の鳥です。
羽毛は白い部分と黒い部分からなり、首筋は黒く赤い頭頂部が特徴です。
飛ぶ姿は純白で美しく北海道の鳥として指定されています。
開拓以前の北海道にはいたるところに湿地があり、あちこちで飛んでいましたからめずらしい鳥でありませんでした。
しかし、明治時代になって屯田兵などの開拓移民が本州から入ってきました。
湿地は開拓され農地になり、昔は、狩猟の規制がなかったので乱獲され、あっという間にタンチョウの数は減り、20~30年の間で姿が見られなくなりましました。
大正13年(1924年)には、釧路湿原に残っていたタンチョウは、わずか10数羽。
あまりにも少なくなったため翌年、この地域を禁猟区としてやっと国の保護政策が始まったのです。
昭和10年(1935年)には、国の天然記念物として指定されました。
昭和27年(1952年)には、繁殖地も含めて「釧路のタンチョウ」として特別天然記念物に指定され、昭和42年(1967年)には、地域を定めず種として特別天然記念物に指定され大切に保護されています。
越冬期には、そのほとんどが釧路地方に飛来し2018年には、約1,650羽が確認されています。
世界の総個体数は3,050羽とされいますので、その半数以上が北海道に生育していることになります。
冬は、餌やりなどの保護活動も行われています
ナキウサギ

「氷河時代の遺物」「生きた化石」とも呼ばれる、北海道にしかいない小動物です。
見た目はネズミに似ていますが上あごの前歯(門歯)の裏側にも歯がついていて歯が二重になっているのでウサギの仲間です。
1万年前以上も前の氷河期に、シベリヤ大陸から氷河伝いに北海道に渡ってきたと思われます。
この頃は氷河が発達して海面が下がっていたため、大陸と北海道は陸続きになっていました。
氷河期が終わり、氷が溶けると海水面が上昇して、北海道は再び島になったのです。
この時ナキウサギは、北海道の涼しい山岳地帯に生き残ったのです。
ナキウサギの生息地は、北海道でも中央部分に限られていて、北見山地、大雪山系の山々、日高山脈や夕張山地などの標高の高い山に多く見られます。
ガレ場といわれる大小の岩が積み重なったところで鳴く可愛い姿が見られるそうです。
エゾ鹿

道内を車で歩くと、よくエゾ鹿の群れに出くわすことがあります。
牧草地で草を食べていたり、時には道路を横断・飛び出しなどもあり、鹿と衝突事故などの話もよく聞きます。
エゾシカは、北海道のみに生息するニホンジカの亜種で、本州に生育する二ホンジカより体が大きくオスは、体調190㎝重さ150㎏くらいの大きさになることもあり。見た目の可愛さと相反して、車の近くに寄ってくるとその大きさにビックリします。
エゾ鹿は、群れで行動しますから出会った時は、1匹だけ行き過ぎてもまだいると判断した方がいいでしょう。
明治初期には、乱獲・大雪などで絶滅寸前にまで数が減ったことがありましたが、今では数も増え道内至る所に生息しています。
野草・どんぐりなどを食べますが食べるものが少なくなると牧草地の草・農作物・木の芽・樹木の皮など草食系の動物ですが・1日5㎏くらいの餌を食べます。
数が増えると段々と被害額も増え深刻な問題になっています。
平成26年(2014年)3月に制定した「北海道エゾシカ対策推進条例」に基づき、 捕獲等による個体数の管理、捕獲個体の有効活用推進など計画的にエゾ鹿対策が行われ、捕獲された鹿はジビエ料理として人気があります。
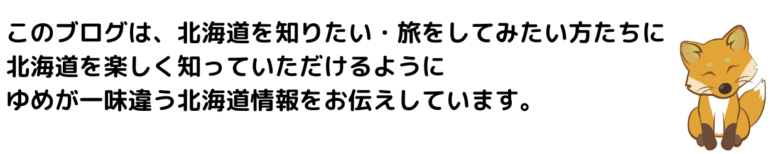



コメント