
「豊平川(とよひらがわ)」は、札幌市の中央を流れている川です。
豊平川は、札幌市と千歳市の境界にある小漁山に源流を発し、定山渓にある豊平峡ダムに入り、札幌市内をゆったりと貫流しています。
札幌中心部あたりに来ると川幅も随分大きくなってきます。
札幌中心部の20キロメートルほど下流で、石狩川に合流したあと日本海に注ぐ長さ72.5キロメートルの石狩川水系の一級河川です。
アイヌの人たちは、この川を「トイェ・ピラ」(崩れた崖)と呼び、豊平川の川岸の一部の呼び名からこの名が付けられたといわれます。
市街地にある河川敷は、豊平川緑地と名付けられレクリエーションとかスポーツ、散策等の憩いの場となっています。
釣りを楽しむ人や親子の水遊びの場などとして、札幌市民に親しまれています。
昔は、大都市に流れ込んでいる川としては、珍しいほどの急流でしたが、幾度も改修工事が行われ、今では川の姿もすっかり近代的な都市河川に変わっています。
大都市札幌市を流れる豊平川には、毎年秋にサケが遡上してきます。
そのサケの自然界での姿などサケについて詳しく学ぶことができる施設が札幌市南区真駒内公園内にあります。
「札幌市豊平川さけ科学館」です。
秋になると豊平川に帰ってくる鮭や、その産卵の様子も間近見ることができます。
この「豊平川 」周辺には、観光に便利なホテルや旅館も多いです。
この記事では、「豊平川 」のサケの遡上についてとその歴史、また「豊平川さけ科学館」の見どころや特徴、などをまとめてみました。
また、観光に便利なおすすめホテル・旅館などもご紹介しますので参考にしてください。
「豊平川」のサケの遡上(そじょう)
豊平川の鮭の歴史

川の周辺では、古代の人がサケを捕獲した魚止柵(うおどめさく)の遺跡が見つかっています。
江戸時代から明治時代にかけては、サケを捕る漁具・漁法も次第に発達し、豊平川でも多くのサケが捕られるようになりました。
鮭は、冬の間に川で生まれ春になると海にでます。
海に出た後は、日本の沿岸にしばらくいますが、その後オホーツク海にいきます。
秋になるとオホーツク海からベーリング海に向かい、そして、ベーリング海とアラスカ湾を行ったり来たりして、3年以上5年くらいたったものが自分が生まれた川に戻ってくるのです。
産卵のために戻ってきますがどうして自分の生まれた川が分かるんでしょうか?
まだはっきりしたことはわかっていませんが、臭いを感じて、生まれた川の臭いが分かるんじゃないかという説もあります。
明治11年(1878)年には、札幌の偕楽園(か い ら く え ん)にふ化場が設置されました。
サケの人工ふ化が試験的におこなわれたのです。
豊平川で捕獲された親ザケから6万粒が採卵されました。
翌年明治12年(1879年)、元気に育った稚魚の中から94尾が豊平川に最初の稚魚の放流が行われました。
豊平川での最初の本格的なサケ増殖事業(親ザケの捕獲と稚魚の放流)は、昭和12年(1937年)から昭和28年(1953年)まで行われていました。
しかしその後、札幌の人口増加にともない、家庭排水や工場排水による水質悪化がひどくなり、事業は中止されました。
川の水が汚すぎて豊平川に上るサケは、全くいなくなったのです。
その後、1970年代に入り徐々に水質が回復してきました。
でも、川はきれいになったのになぜか鮭は戻りませんでした。
昭和49年(1974年)からは、なんとか鮭が豊平川に戻ってきて欲しいと「カムバックサーモン」という市民運動が始められました。
人工ふ化した稚魚を放流するという活動です。
昭和54年(1979年)春には稚魚の放流が約30年ぶりに再開され、昭和56年(1981年)秋には、そのサケが親ザケになって豊平川に帰ってきました。
昭和59年(1984年)に運動の拠点施設として札幌市豊平川さけ科学館が作られ、放流事業を引き継ぎました。
そうして、昭和60年(1985年)には、やっと自然産卵も確認されるようになったのです。
札幌市豊平川さけ科学館

昭和59年(1984年)10月6日開館した「札幌市豊平川さけ科学館」はサケや水辺の生きものを身近に感じてもらおうという施設です。
2 匹のサケ稚魚が向かい合い、中央には豊平川の流れをイメージしたブルーとパープルのステンドグラスが配された印象的なデザインの建物で外観はログハウス調です。
サケの自然界での姿などサケについて詳しく学ぶことができ、秋になると豊平川に帰ってくる鮭や、その産卵の様子も間近見ることができます。
ふ化した稚魚は春になると子供たちの手で豊平川に放流されるのです。

さけ科学館では、鮭のほかに、世界のサケの仲間がおよそ20種類と、豊平川に生息している魚・ザリガニ・カエルなどおよそ30種類が飼育されていて、常時展示されています。
「豊平川 さけ科学館」へのアクセス!
「さけ科学館」までのアクセスです。
札幌駅から地下鉄とバスを利用する場合
大人420円 子ども210円 約25分
地下鉄南北線終点「真駒内駅」からじょうてつバス [南90]・[南95]・[南96]・[南97]・[南98]・[環96]系統のいずれか乗車、「真駒内競技場前」停留所下車、徒歩4分
※ バス停をおりると、道路の反対側がさけ科学館です.
付近に横断歩道はありません.オープンスタジアム側からアンダーパスをご利用ください。
札幌駅前からバスを利用する場合
大人210円 子ども110円 約40~50分
じょうてつバス〔南55〕「札幌駅前」発・・・①「川沿1条1丁目」下車・・・徒歩約8分
じょうてつバス〔南54〕「札幌駅前」発・・・②「真駒内本町」下車・・・徒歩約10分
じょうてつバス〔快速7・快速8〕「札幌駅前」発・・③「藻岩高校前」下車・・徒歩約8分
車を利用する場合
札幌市内中心部から約25分
石山通(国道230号線)を定山渓方面に南下 川沿アンダーパス手前で左側道に入り、アンダーパス上の信号(コナミスポーツ・イオンが目印)で左折、五輪大橋を渡ってすぐ、左側に駐車場があります。
開館時間
9時15分から16時45分
休館日
毎週月曜日(祝休日の場合は次の平日)
年末年始(12月29日から1月3日)
入館料
無料
駐車場
真駒内公園B駐車場(1172台)
平日および冬期間(11月4日から4月28日)
無料
4月29日から11月3日
土日祝休日のみ有料
「豊平川 」周辺のおすすめホテル
「豊平川 」の周辺には、素敵なホテルや旅館がたくさんありますので、おすすめをご紹介します。
ホテルライフォート札幌
この「ホテルライフォート札幌」は、中島公園の眼の前にあるホテルです。
札幌の夜の繁華街すすきのも徒歩圏内で立地の良いホテルです。
一番の特徴は窓から広がる札幌の景色で、緑の多い中島公園を見下ろすこともできます。
最近の札幌のホテルは料金が高騰。
そんな中でコスパの良さが有名で、宿泊費が高いと思っている人におすすめです。
シングル・ツイン・セミダブルルームとお部屋もいろいろそろっています。
清潔感のあるお部屋はこちらからご覧ください。
ホテルノースシティ
この「ホテルノースシティ」は、中島公園に近い立地で地下鉄中島公園駅がすぐ近くにあります。
札幌駅から車で10分ほどです。
おしゃれでちょっと高級感のあるお部屋が人気です。
お部屋の様子は、こちらからご覧ください。
札幌観光の拠点にも便利ですね。
ビオス 館/民泊【Vacation STAY提供】
この「ビオス 館/民泊【Vacation STAY提供】」は、民泊型の宿泊施設です。
お部屋によって雰囲気も違いますし、お部屋によって設備も変わってきます。
こちらからお部屋の写真をご覧いただけます。
「豊平川 」のサケ科学館の歴史やアクセスのまとめ
「豊平川」は、北海道の首都札幌市の中央を流れている川です。
豊平川は、札幌市と千歳市の境界にある小漁山に源流を発し、定山渓にある豊平峡ダムに入り、札幌市内をゆったりと貫流する石狩川水系の一級河川です。
アイヌの人たちは、この川を「トイェ・ピラ」(崩れた崖)と呼び、豊平川の川岸の一部の呼び名からこの名が付けられたといわれます。
市街地にある河川敷は、豊平川緑地と名付けられレクリエーションとかスポーツ、散策等の憩いのばとして、札幌市民に親しまれています。
200万人もの人が暮らす大都市を流れる川に、サケが遡上するのは大変珍しいことです。
毎年、10月初旬〜11月末になると札幌のいくつかの河川には、鮭が遡上してきます。
この豊平川にも1000~2000尾の鮭が遡上してくる姿を見ることが出来ます。
川の周辺では、古代の人がサケを捕獲した魚止柵(うおどめさく)の遺跡が見つかっています。
江戸時代から明治時代にかけては、サケを捕る漁具・漁法も次第に発達し、豊平川でも多くのサケが捕られるようになりました。
しかし、人口が増えると川の水が汚れ鮭の姿は見れなくなってしまったのです。
1970年代に入り徐々に水質が回復してきましたが鮭は戻りませんでした。
そこで、人工ふ化した稚魚を放流するという活動「カムバックサーモン」運動が始まりました。
昭和56年(1981年)秋には、そのサケが親ザケになって豊平川に帰ってきました。
そのサケの自然界での姿などサケについて詳しく学ぶことができる「札幌市豊平川さけ科学館」が札幌市南区真駒内公園内にあり、秋になると豊平川に帰ってくる鮭や、その産卵の様子も間近見ることができます。
秋になったら豊平川に掛かる橋からそっと川底を覗いてみてください、必死に上流に向かう鮭の姿を見ることができるでしょう。
その豊平川の鮭と周辺のおすすめホテル情報をご紹介しました。
豊平川 を訪れる際には、秋にはぜひ豊平川をのぞいてみてくださいね!
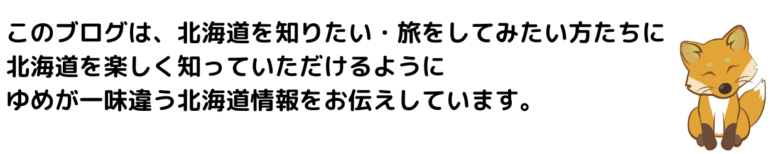







コメント