
「松前町(まつまえちょう)」は、北海道の最南端の渡島管内にあります。
昔は、「大館」と呼ばれていました。
16世紀後半に松前氏はアイヌとの交易を独占し、蝦夷地(北海道)の支配を確立しました。
江戸時代に入り、松前藩が成立すると、この地が藩の政治・経済・軍事の中心地となりました。
五世慶広が、文禄二年(1593年)に初代の松前藩主に任命されました。
この時に地名を「松前」と改めたのです。
江戸時代には、城下町として栄えた「松前町」は、日本最北の城下町と桜の町として有名です。
今回は、「松前町」の歴史や松前城。
松前町でないと食べれない海苔や「松前町」の観光スポット。
旅をするのに最適なお宿もご紹介しますね。
道内唯一の城下町・北海道松前町

「松前城」は、北海道でただ一つのお城です。
最初の松前城は、慶長5年(1600年)に松前 慶広(まつまえ よしひろ)が、6年の年月をかけ構築したものです。
当時は「福山城」と呼ばれて、城というほど堅固なものではありませんでした。
江戸時代後期、ロシアの南下政策による脅威が高まりました。
そのため、蝦夷地の防備が幕府の重大関心事となりました。
それと共に福山城の近代的な大改修が企画されたのです。
幕府の命を受けた松前崇広は、西洋式の砲術にも対応できる近代的な城を築くため、、古い城を取り壊しました。
設計は高埼藩の兵学者、市川 一学(いちかわ いちがく)が行い、安政元年(1854年)完成しました。
この城は、日本で築かれた旧式建築としては最後のもので、面積約7万7800平方メートル、本丸、二の丸、三の丸、楼櫓、城門、砲台7座を備えていました。
特に大砲に対する防御力を強めている点がほかの城と違うところです。
この時から「松前」は、城下町として栄えたのです。
松前城と戊辰戦争
明治元年(1868年)10月、幕府脱走軍は、榎本釜次郎武揚(えのもとかまじろうたけあき)を首領として蝦夷地(現森町鷲ノ木)に上陸しました。
五稜郭を占拠し、その後、かつての新選組副長土方歳三を長とする陸軍隊・額兵隊(がくへいたい)の主力が、福山城へ向けて進撃を開始したのです。
松前藩は死力を尽くして防戦しましたが、遂に落城し、城内の一部と寺町を焼いて敗走ました。
明治2年(1869年)4月には、幕府脱走軍の占拠する福山城を官軍が奪回するなど、2年間にわたる戦禍は、城下町の3分の2を焼き、城内にも大きな被害を与えたのです。
天守
松前城の天守は、江戸時代末期に建てられたもので、本州の城に比べててみるとずいぶん小ぶりな造りでした。
現存していた天守は昭和24年(1949年)に焼失し、現在の天守は昭和36年(1961年)に復元されたものです。
現在は松前城資料館として公開されていて、松前藩やアイヌとの交流、戊辰戦争などの資料が展示されています。
本丸御門(大手門)と石垣と堀

明治8年までに、城内は開拓使の命によって取り壊しとなっっています。
その際残された三層天守と本丸御門および東塀が昭和16年(1941年)に国宝指定となりました。
しかし、昭和24年(1949年)6月5日、役場火災の飛火によって天守・東塀は焼失し、本丸御門(大手門)を残すのみとなりました。
福山城唯一の遺構となった本丸御門(大手門)は、昭和25年(1950年)8月29日重要文化財に指定されています。
切妻造り、銅板葺き、三間一戸両脇戸付き櫓門。
南に面し、東方との三重櫓(天守)との間に塀が取りつけられています。
城の防御設備として、海側に面した天然の断崖と、陸側を囲む石垣や堀が設けられています。
特に本丸周辺の石垣は、当時のままの姿を今も残しています。
松前町で絶対食べたい海の香りがする海苔

北海道松前町では、地元産の「天然岩海苔(寒のり)」が人気です。
松前町のお母さんが毎年1月から4月にかけて、極寒の松前の海に入り一つ一つ丁寧に摘んで取った岩のりです。
手摘みの天然岩海苔をすだれに並べ自然干しで、手間ひまかけて作られたものです。
市販の海苔と比べると手すきなので厚みが全然違います。
色の黒さ、風味の良さ、磯の香りの強さどれをとっても数段上。
「岩海苔は格が違う」と昔から知る人が知る有名な天然岩海苔です。
松前町にある道の駅『北前船』や一部商店でしか取り扱いがない貴重な海苔です。
機会があったら是非食べてみたいですね。
松前町の名所・観光スポット
白神岬
白神岬(しらかみみさき)は、北緯41度23分東経140度11分、北海道最南端に位置する岬です。
津軽海峡対岸の青森県竜飛崎までわずか19.2キロ、晴れた日には対岸の風車まで見通すことができる絶景スポットとして知られています。
また、津軽海峡は渡り鳥にとって難所中の難所であり、津軽海峡に突き出た白神岬は鳥たちが長い年月をかけて選択した渡りの主要ルートとなっています。
春にはシベリア方面へ、秋には越冬のため本州へ年間およそ100万羽300種類以上の野鳥が津軽海峡を渡ります。
晴れた日には下北半島や函館山が見え、夕暮れ時には美しい夕日が海を染めるロマンチックな風景が広がります。
岬には記念碑が設置されています。
北海道最南端の地を訪れ、壮大な海の景色を見れば、思わず「津軽海峡冬景色」の一節が頭をよぎる事でしょう。
「ごらんあれが竜飛岬北のはずれと・・・」
北の荒波を見ながら過ごす一時に心癒されてみませんか?
北前船ゆかりの歴史ある町並み松前町の寺町
松前城の北側には道内で唯一の寺町が広がっていいます。
松前藩の城下町として発展した地域で、多くの寺院が集まる歴史的なエリアです。
寺町はもともと城の山側を守るとともに、城から見て鬼門(北東)にあたる位置に配置することで仏の加護を求めるものでした。
現在は阿吽(あうん)寺、龍雲院、法幢(ほうどう)寺、法源寺、光善寺の5つの寺院が残っています。集中的に配置された寺とそれらをつなぐ石垣と石畳が続く寺町の風景は、京都や鎌倉のような雰囲気もあります。
春には松前城の桜とともに、歴史ある寺町の風景を楽しむことができ、周囲には樹齢数百年はあるかと思われる大きな木々が鬱蒼と生い茂り、夏も暑さをしのげるので散策にぴったりのエリアです。
江戸の松前を再現!「松前藩屋敷」
★問合せ先
松前観光協会
★電話番号
0139-42-2726
★利用時間
9:00~17:00(最終入館16:30)
★休日
11月下旬~4月上旬
★利用料金
入園料大人360円、小中学生240円、幼児無料
※甲冑着付体験
(大人1500~2000円、幼児1000~1500円)」
武将・足軽、お殿さま、お姫さまなどに扮して、時代劇気分が味わえます。
※松前の伝統料理
「松前漬づくり体験(1500円・要予約)」
★駐車場
無料駐車場あり(150台)
松前町おすすめホテル旅館
温泉旅館 矢野
「温泉旅館 矢野」は、食事が大人気のお宿です。
リーズナブルなプランから、地元松前の海の幸を堪能できるプランなど、たくさんのプランから選ぶことが出来ます。
特に、松前で上がるまぐろは、津軽海峡で捕れます。
青森側の大間町で水揚げされると、お正月の初セリで何億という値段で取引される「大間まぐろ」と同じ海域で捕れる天然本マグロです。
この「松前まぐろ」がつくプランもあります。
飛行機を利用してくる方は、パックが断然お得です。
THE VILLA MATSUMAE
「THE VILLA MATSUMAE ^」は、大きな窓から津軽海峡を見ながらゆったりくつろげる、一棟貸し切りのホテルです。
1名から最大15名まで対応できますので、家族旅行やグループ旅行には、ぴったりですね。
キッチンも設けられていますので自分たちで料理したり、近くにコンビニもあるのでとても便利です。
松前町のまとめ
「松前町(まつまえちょう)」は、北海道の最南端の渡島管内にあります。
「松前」は、城下町として栄え、北海道でただ一つ「松前城」が築城された町です。
昭和24年(1949年)6月5日、役場火災の飛火によって天守・東塀は焼失してしまいました。
本丸御門(大手門)や石垣は、現在でも当時のまま残されています。
昭和36年(1961年)には、天守が復元され城の町・桜の町として大人気の場所となっています。
北海道松前町では、地元産の「天然岩海苔(寒のり)」が人気です。
松前町のお母さんが毎年1月から4月にかけて、極寒の松前の海に入り一つ一つ丁寧に摘んで取った岩のりです。
手摘みの天然岩海苔をすだれに並べ自然干しで、手間ひまかけて作られたもので普段食べている市販の海苔とは、風味が全く違います。
手作りのため数量も限られていますが、もし巡り合えた時は旅の思い出にぜひ食べてみたいですね。
また、「松前城」は勿論のこと、北海道最南端の岬「白神岬」。
道内で唯一の「寺町」や江戸時代の松前藩の城下町の様子を再現した歴史的テーマパーク「松前藩屋敷(まつまえはんやしき)」などの観光スポットもたくさんあります。
歴史ある街で、のんびりと過ごすのもいいですね。
今回は、北海道でただ一つの城下町「松前町(まつまえちょう)」の松前城や手作りの海苔!
また、付近の観光スポットやおすすめ旅館についてお話ししました。
潮の香り漂う「松前町(まつまえちょう)」
ぜひ、一度は訪れてみてください。
「松前町」の桜・桜まつりについては、こちらの記事をお読みください。

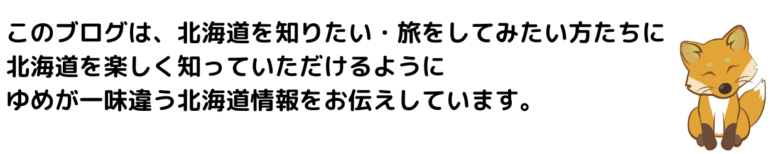




 ANA楽パック
ANA楽パック JAL楽パック
JAL楽パック
