
函館市にある「五稜郭(ごりょうかく)」は、「五稜星(ごりょうせい)」の形をした公園です。
「五稜星」というのは、蝦夷地を開拓していた開拓使たちが、北海道へ向かうときに目印にしていた北極星のことなんです。
「五稜郭」は榎本武揚、大鳥圭介、新選組の副隊長土方歳三などが奮戦した古戦場として人々に知られています。
大正3年(1914年)からは一般開放され国の特別史跡の指定を受けています。
この、古戦場五稜郭に、函館市が公園の設備をした後、函館毎日新聞社から発刊1万号を記念し、桜の木五千本贈られ植えられました。
それからは、全国でも有名な桜の名所となったのです。
春5月ともなりますと「五稜郭」には、桜の花が桜花爛漫と咲き誇り、そのたたずまいをお堀に写してまさに絢爛なる春の宴です。
桜を追うようにつつじ、藤と見事な花を咲かせるのです。
夏は、お堀にボートを浮かべる人もおり、市民による、歴史を題材としたイベントの会場としてなど四季を通じて利用されています。
また函館の観光スポットとしていつも賑わいを見せています。
そんな市民の憩いの場「五稜郭」がどうしてできたのか?
この「五稜郭」を舞台に戊辰戦争の最後の戦いとなる箱館戦争がどうして行われたのか?
「五稜郭」に作られた「函館 奉行所」のいまなど「五稜郭」についていろいろお話しします。
五稜郭建築の訳は?

長い間、鎖国の扉を閉ざしていた徳川幕府が、開港条約を結んでからは長崎、横浜の港はもちろんのこと、この函館にもペリー提督をのせたアメリカの艦隊を始め数々の外国船が姿を見せるようになりました。
そこで幕府は、蝦夷地を管理して外国から守るため「箱館奉行」を配置しました。
その役所や役宅は密集した市街地にありました。
また港に近く寒気が厳しいなどの生活環境も悪く。
上陸した外国人による市街地の遊歩によって役所が見透かされるといった幕府の威厳などの問題点が多くありました。
なにより、港に至近の位置のため艦船からの標的になりやすいといった防衛上の危機感などの理由から、役所と役宅を内陸の平坦地へ移転させることになりまた。
新しい役所は、四方に土塁を巡らしその中に役所を建設します。
附近の河川から水流を引き込み周囲を水堀で囲む形が計画されました。
五角形の星の形です。
この星型の先の5ヶ所に砲台を置いて守ると、死角がないという理由から「五稜星」の形になりました。
幕府は、武田斐三郎に設計と監督をさせることにしました。
武田は、フランス軍人からの助言に独自の工夫も加えて安政4年(1857年)に着工します。
堀・石垣などの土木工事、附近の河川から水流を引き込むための治水工事が完成しました。
その後、土塁内への役所や附属施設の建築、土塁北側一帯への役宅の建築などが進められました。
元治元年(1864年)工事は、7年の歳月をかけほぼ完成しました。
箱館山の山麓市街地にある旧役所が移転し、「箱館御役所」(通称「箱館奉行所」)として蝦夷地の政治を担う場所となったのです。
五稜郭の戦い 戊辰戦争から箱館戦争へ

箱館戦争は、新天地を求めた男たちの戦いでした
徳川300年の歴史が終わりを告げた慶応3年(1867年)大政奉還の際、これに対して旧幕臣の領地にしようと嘆願しましたが聞き入れられませんでした。
大政奉還に真っ向から反対であった旧幕臣や新選組の同士を含めて総勢3千余名が軍艦6隻に乗り、明治元年(1868年)8月、東京品川を出発したのでございます。
同年10月20日に蝦夷地の鷲ノ木(わしのき)(現茅部郡森町。かやべぐんもりまち)へ上陸いたしました。
翌21日榎本武揚を戦闘に旧幕府脱走軍艦隊は、破竹の勢いで箱館に攻め入りました。
戊辰戦争の最後の戦いとなる箱館戦争が開始されたのでございます。
時の箱館府は、五稜郭にありましたので、蝦夷地へ上陸した旧幕府脱走軍は,数手に分かれて五稜郭を目指ました。
10月26日には箱館府兵が青森口へ逃げて無人の五稜郭を占拠することになりました。
松前や江差方面も相次いで旧幕府脱走軍が占拠することになり、12月15日には榎本武揚を総裁とする蝦夷地仮政権が樹立されました。
しかし翌、明治2年3月朝廷から脱走軍を追い打ちせよとの大命が下りましたので、幕府脱走軍は賊軍の汚名の下に総勢一万余名、艦船10隻の官軍を迎え撃つことになったのです。
この蝦夷地を根拠地として、新しい天地を築こうとの夢を守るため必死で戦いました。
脱走軍も5月11日官軍の総攻撃に力尽き、矢折れついに降伏の止むなきに至ったのです。
幕末の頃から明治にかけてここは歴史の渦巻く場所だったのです。
人間臭いドラマが約半年間、この地を舞台に繰り広げられました。
ロシア防備が目的だった城で幕府脱走軍と新政府軍が戦うとは・・・
「こんなつもりじゃなかった!」と築城者の武田斐三郎もさぞ嘆いていたことでしょう。
歴史とはえてしてこんな皮肉を平然と行うものでございます。
新選組の「鬼の副長」として恐れられ、旧幕府軍の榎本武揚らとともに明治元年(1868年)箱館(現在の函館)にやってきた土方歳三。
陸軍奉行並の要職に就いて箱館戦争で活躍したものの、翌年の旧暦5月11日(現在の暦で6月20日)、新政府軍による箱館総攻撃が始まった日に戦死しました。
その男気から、今もたくさんの人に愛されつづける土方歳三。
そして、近代日本の夜明けに尊い血が流された、明治新政府軍と旧幕府軍による戊辰(ぼしん)戦争の最後の戦いの地・函館。
毎年5月中旬には、この戦いで散った志士たちをしのび、箱館五稜郭祭が開催されます。
碑前供養や、土方歳三コンテスト全国大会のほか、ペリーの箱館来航から箱館戦争終結までを題材に、総勢約1000人が当時の衣装を身にまとって街を練り歩く維新パレードが行われるのです。
五稜郭の奉行所の復元

「箱館奉行所」旧幕府脱走軍降伏の2年後、明治4年(1871年)に解体されました。
五稜郭は、大正11年(1922年)に国指定史跡とされ、さらに昭和27年(1952年)には、「史跡のうち学術上の価値が特に高く、我が国文化の象徴たるもの」として、北海道では唯一の特別史跡に指定されました。
国宝に準ずる文化財として保存整備事業が進められ、石垣の修理や橋の架け替え、更には五稜郭に関る絵図面や文献資料の調査を経て、昭和60年(1985)から郭内の遺構調査が進められました。
五稜郭および箱館奉行所は、江戸幕府が直接かかわって築造し、さらに幕末という近代の史跡であることから多くの資料が存在すると考えられました。
また、奉行所が取り壊された後も、五稜郭は積極的には活用されず公園として一般開放されましたが、国の史跡として厳しい開発規制がかけられていたために、石垣、土塁もよく保存され、遺構も残存することになりました。
国の特別史跡・五稜郭跡の歴史的意義や価値を伝えるには、奉行所の復元をふくめた整備が必要であると考えられてきました。
この結果に基づいて平成22年(2010年)、庁舎全体の建築面積の3分の1ですが、建物正面を中心とした範囲で、当時と同じ場所、伝統工法、同じ材木を使用して御役所(奉行所)庁舎の高い精度での復元がされたのです。
特別史跡である五稜郭では、土地を改変することが原則認められていませんので、遺構を保護した上に厚さ25センチメートルのコンクリート耐圧版を敷き、それを基礎として建てられました。
箱館奉行所は、かつてと同じ場所に復元されています。
つまり、建物の真下には、当時の遺構が残っているのです。

五稜郭の完成から約150年を経て、箱館奉行所は復元され昔の姿が蘇りました。
築造当時の状況を伝えるものは、土塁・石垣、堀割、アカマツ、1棟の土蔵(兵糧庫)のみとなってしまいましたがお散歩などしながら、ぜひ昔の姿を想像してみてください。
箱館奉行所内は見学コースも設けられており、建物の中を隅々まで見学していただく事ができます。
要所には、ガイドさんもいて、よりいっそう詳しくご覧いただけるでしょう。
付近の美味しいもの
「五稜郭」付近の美味しいお店をご紹介します。
あじさい 本店
函館というと塩ラーメンといわれるほど。
ラーメン屋さんはたくさんありますが、「あじさい」というと誰もが知っているほどの老舗です。
人気は、やっぱり塩ラーメン。
昆布などの魚介の旨味を利かせた、豚骨や鶏ガラのスープ。
透き通ったスープにたまご麺、まさに王道の塩ラーメンです。
函館麺厨房 あじさい 本店
— toma (@0329Tohma) November 27, 2020
@五稜郭公園前
特塩拉麺 pic.twitter.com/90PlD17wFe
ピーベリー
五稜郭公園に面してお店があるのでロケーションばっちりのカフェ。
美味しい焼きたてパンが人気のお店です。
五稜郭に行った時には、ぜひ寄ってみてね。
「五稜郭公園」付近のホテル
五稜郭の近くにあるホテルをご紹介します。
ホテルBRS函館 五稜郭タワー前
五稜郭タワーのすぐ前にあるホテルです。
バスも電車も停留所がすぐ近くなので、函館観光にもとっても便利ですね。
朝のお散歩に五稜郭を歩けますよ。
お部屋も清潔だと口コミがたくさんあります。
函館 十字屋ホテル
このホテル、昔は三越函館店でした。
周りには、コンビニや飲食店などがあるので夕食を考えると便利ですね。
無料の朝食とコーヒーのサービスがあります。
珈琲は美鈴珈琲、北海道で一番の老舗珈琲店です。
ホテルマイステイズ函館五稜郭
「ホテルマイステイズ函館五稜郭」は、市電の「五稜郭公園前」の前に建つホテルです。
綺麗に手入れされたお部屋が人気です。
お部屋の様子はこちらからご覧ください。
朝から並ぶイカ刺しや函館名物塩ラーメンなどが並び美味しいと人気です。
おいしそうなお食事の写真は、こちらからご覧ください。
函館五稜郭のまとめ
函館市にある「五稜星(ごりょうせい)」の形をした「五稜郭(ごりょうかく)」公園は、榎本武揚、大鳥圭介、新選組の副隊長土方歳三などが奮戦した古戦場です。
元治元年(1864年)7年の歳月をかけ完成しました。
蝦夷地を管理して外国から守るため「箱館奉行」が建てられました。
明治元年(1868年)には、戊辰(ぼしん)戦争最後の戦いの函館戦争が繰り広げられました。
明治2年、5月11日脱走軍は官軍の総攻撃に力尽き、矢折れついに降伏の止むなきに至ったのです。
「函館奉行所」は、明治4年(1871年)に解体されました。
しかし五稜郭は、大正11年(1922年)に国指定史跡とされ、さらに昭和27年(1952年)には、「史跡のうち学術上の価値が特に高く、我が国文化の象徴たるもの」として、北海道では唯一の特別史跡に指定されました。
国宝に準ずる文化財として保存整備事業が進められたのです。
国の特別史跡・五稜郭跡の歴史的意義や価値を伝えるには、奉行所の復元をふくめた整備が必要であると考えられてきました。
この結果に基づいて平成22年(2010年)、庁舎全体の建築面積の3分の1ですが、建物正面を中心とした範囲で、当時と同じ場所、伝統工法、同じ材木を使用して御役所(奉行所)庁舎の高い精度での復元されたのです。
建物の真下には、当時の遺構が残っています。
「五稜郭公園」は、今では全国でも有名な桜の名所となったのです。
「五稜郭公園」と周辺のおすすめホテル情報をご紹介しました。
こんな歴史的な場所を見てみたいと思われた方も多いと思います。
そういう方は、ぜひ足をお運びください。
「函館市」のまとめ記事は、こちらをご覧ください。

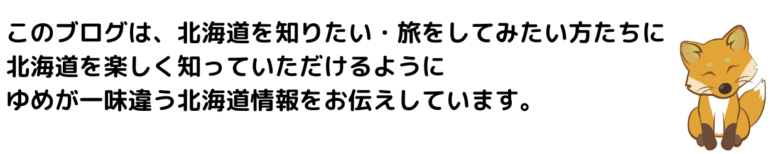






コメント