
豊平峡は、豊平川の上流、定山渓から南へ3キロほど入ったところにあります。
岩壁が百数十メートルの安山岩で、長い槍を立てて並べたように見えます。
針葉樹、潤葉樹の入り混った原始林は、大雪山国立公園の層雲峡を思わせ、昔から地獄に通じると、恐れられていた景勝地です。
春、渓谷に茂る広葉樹は新緑に色どられ、秋、紅葉に映える山々に、美しく流れる清流は、支笏洞爺国立公園唯一の渓谷として特別保護地に指定されています。
そんな美しい渓谷に豊平川の治水である豊平峡ダムがつくられました。
湖と緑が織りなす雄大な自然の景観美あふれる、札幌有数のレジャー・スポットとなったのです。
特に紅葉の季節は美しく、林野庁の「水源の森100選」や「ダム湖100選」にも選定されました。
今回は、大人気の札幌市民の水がめ豊平峡のダムについて。
ダムでの見どころや豊平峡の一番きれいな季節秋の紅葉のこと。
札幌から豊平峡までのバス情報などを詳しくご紹介します。
札幌市民の水がめ豊平峡ダム
奥深い原始林の中にコンクリートのお城を思わせるところがあります。
そこは二百万都市札幌の「水がめ」ともいわれる豊平峡ダムです。
昭和42年(1967年)の春、札幌市、北海道開発局、北海道電力が共同で建設し、昭和46年(1971年)秋に8億5千万円
の工費で完成しました。
完成したダムは、堤長305m堤高102.5mで34階建てのビルと同じくらいの高さがあります。
豊平川の流れをせき止めてできた人造湖は「定山湖」札幌ドームの30個分もの水をたたえています。
洪水調節、上水道、電源開発の多目的ダムです。
洪水にならないように、下流の豊平川へ流れる水を調節しています。
ダムの水は上水道を通り飲料水として使用されています。
このダムは、特に上水道の水源地としての役割が大きく札幌市の給水需要は豊平川によって98%もカバーされています。
豊平峡ダムから、豊平峡発電所まで水を送って最大出力は5万kwの水力発電をしています。
豊平峡 電気バス

豊平峡では、支笏洞爺国立公園内にあるので自然環境保全を考え、昭和51年(1976年)から電気自動車を導入しました。
豊平峡ダム入口から豊平峡園地までの約2kmは、自家用車で行くことはできません。
一般車両・バイク・自転車の乗り入れが通年禁止です。
この先は、徒歩か電気バスを利用します。
電気バスに乗り10分弱ですが、周りの自然を楽しみながらのんびりと向かいます。
途中の見どころも案内してくれますよ。
徒歩で行くと30分ほどですがトンネルが2か所あってちょっと薄暗いです。
何人かで行くんでしたら大丈夫ですね。
電気バスは、現在3代目で豊平峡で5台運行しています。
豊平峡ダム電気バスの時刻表
バスの時刻表はありません。
約15分〜30分間隔で運行しています。
2023年運行期間
5月1日(月)~11月3日(金・祝)
運行時間
9:00~16:30(上り最終便16時00分)
駐車場(無料です)
一般車両・バイク・自転車はすべてここに止めます。
250台
料金
大人 往復 700円 片道 400円 ・中学生以上
小人 往復 350円 片道 200円 ・未就学児無料
シニア(65歳以上) 640円 ・往復のみ(年齢がわかるものを提示)
障がい者 大人 350円(往復) 小人 170円(往復)
JAFの優待割引乗車料金で大人60円引・小人30円引になります。
ペットはケージに入れるとバスへ乗車できます。
豊平峡 の楽しみ方

ダム放流を見よう!
豊平峡ダムでは、毎年6月1日~10月31日まで、「観光放流」を実施しています。
水しぶきを上げ落下するダムの放水は、豪快ですよ。
曜日や時間帯によって放水量が変わりますのでこちらチェックしてください 観光放流時間帯
※洪水対応などによってダム放流を行う場合は、観光放流を中止します。
リフトカーで展望台へ!
9:00~16:20まで無料で運行されている「豊平峡リフトカーひぐま号」で「豊平峡展望台」に行ってみましょう。
「豊平峡ダム」と「ダム湖」に放水の様子も一望できます。
「豊平峡展望台」からは、遊歩道を歩いて10分ほどでさらに高い「渓谷展望台」に行くことができます。
「豊平峡展望台」までは、遊歩道を歩いていく事もできますよ。
ダムカードをもらおう!
豊平峡ダム資料室で令和5年11月2日までダムカードを配布中です。
平日 9:00~16:30 土日祝祭日は休館になってます。
おひとり様1枚限りですよ。
豊平峡ダムの素晴らしい紅葉

豊平峡の紅葉は、北海道屈指の紅葉スポットです。
秋になると木の葉が赤や黄色に色づきはじめ紅葉が始まります。
色づく木は、「落葉樹」で秋になって寒暖差の大きな日が増えると色付きが鮮やかになります。
北海道は、秋になると急激に日中と朝晩の寒暖差が大きくなるのでより鮮やかな紅葉が見られます。
赤、黄色、オレンジとその中に一年中葉をつけたままの「常緑樹」の緑が加わり、そのバランスが見事です。
紅葉がきれいだと人気の定山渓温泉の定山渓観光協会が、五大紅葉の一つに選んでいるほどです。
定山渓観光協会の公式サイトはこちら
紅葉の深まる10月に入ると休日だけでなく平日にも、豊平峡駐車場が満車になることもあります。
そこで、定山渓観光案内所から豊平峡ダムまでのシャトルバス・豊平峡ダムライナーが運行されています。
10月だけの期間限定ですが豊平峡に紅葉を見に行くのには、とっても便利です。
豊平峡公式サイトでは、駐車場の混雑状況や紅葉の色づき情報なども発信していますのでチェックしてみてください。
豊平峡公式サイトはこちら
秋のうららかな天気の日に絶景紅葉スポットでリフレッシュするのもいいですね。
豊平峡へのバス
札幌市から定山渓温泉を通り豊平峡温泉までのバスがあります。
・じょうてつバスのカッパライナー号
・じょうてつバスの豊平峡温泉行路線バス(快速7J-H)
札幌駅から豊平峡温泉までの料金は、大人860円 小人430円
じょうてつバス公式ホームページ
(乗車時間:通常80分)
豊平峡温泉から豊平峡ダム入口までは、およそ3キロあります。
この区間は、バスがありませんので徒歩で行くしか方法がないです。
豊平峡までのバスカッパライナー号

カッパライナー号は、予約制です。
予約はこちらからとれます。
電話予約は、0120-737-109 [フリーダイヤル]
(電話受付時間:9:00から17:00)
札幌駅から豊平峡温泉までの料金は、大人960円 小人480円
乗車時間は、およそ80分です。
札幌駅発車時間
・9:40 ・10:30 ・11:55 ・14:00 ・ 15:00
豊平峡温泉発車時間
・12:15 ・ 13:15 ・ 14:24
カッパライナー号についてはこちらをご覧ください。
札幌駅バスターミナルは駅周辺の工事ため閉鎖されています。
乗り場は、駅周辺に変わっていますのでご注意ください。
乗り場は、こちらからご覧いただけます。
豊平峡ダムライナー
定山渓観光案内所から豊平峡ダムまでのシャトルバス・ダムライナーが秋期間運行されています。
2023/10月1日(日)~10月29日(日)
詳しくはこちら
料金
①バス往復券=600円(大人、子供同一料金)
②豊平峡ダム電気バス往復券+バス往復券 セット=1200円(大人のみ)
定員 各便65名(先着順)
所要時間 2時間(定山渓観光案内所発着)
シャトルバスもハイブリッドバスで運行しています。
豊平峡の美味しいお店
豊平峡ダムにあった「だむみえーる」は、現在営業していません。
豊平峡で食事ができるお店は、豊平峡温泉にある「お料理cuisine」です。
温泉に入らないで食事だけの方もたくさんいます。
名物は、インドカレーにナン。
カレーの種類も多いしナンも最高に美味しいです。
カレーはちょっと苦手という方にも江丹別産そば実を使った十割そばがあります。
ジンギスカンもあるので驚きです。
豊平峡に行った時には。食べてみてくださいね。
定山渓温泉のホテル
2023年定山渓温泉に出来た新しいホテルをご紹介します。
定山渓 ゆらく草庵
2023年2月グランドオープンのホテルです。
全室天然温泉風呂付きの和風の湯宿で廊下はすべて畳敷きです。
温泉が自慢で大浴場には、打たせ湯・サウナ・岩盤浴まであります。
貸切露天風呂も4つもあります。
各階に枕処があって好きな枕を選べます。
翠巌(すいがん)
2023年6月にオープンしたちょっと贅沢な全室スイートの宿です。
部屋数は7室で全てのお部屋に温泉がついています。
森林に囲まれていてお部屋の窓にも緑がいっぱいです。
サウナ付きのお部屋もありますよ。
食事のしゃぶしゃぶは、ミシュランシェフが考案したメニューです。
豊平峡のまとめ
豊平峡は、豊平川の上流、定山渓から南へ3キロほど入ったところにあります。
豊平川の治水である豊平峡ダムを中心に湖と緑が織りなす雄大な自然の景観美あふれる、札幌有数のレジャー・スポットです。
特に紅葉の季節は美しく、林野庁の「水源の森100選」や「ダム湖100選」にも選定されました。
原始林の中に札幌の「水がめ」ともいわれる豊平峡ダムはあります。
洪水調節、上水道、電源開発の多目的ダムで、特に上水道の水源地としての役割が大きく札幌市の給水需要は豊平川によって98%もカバーされています。
豊平川の流れをせき止めてできた人造湖は「定山湖」札幌ドームの30個分もの水をたたえています。
豊平峡の楽しみ方。
・ダム放流 豊平峡ダムでは、毎年6月1日~10月31日まで、「観光放流」を実施しています。
・リフトカーで展望台へ
9:00~16:20まで無料で運行されている「豊平峡リフトカーひぐま号」で「豊平峡展望台」に行ってみましょう。
「豊平峡ダム」と「ダム湖」に放水の様子も一望できます。
「豊平峡展望台」から、遊歩道を歩いて10分ほどでさらに高い「渓谷展望台」に行くことができます。
「豊平峡展望台」までは、遊歩道を歩いていく事もできますよ。
・ダムカードをもらおう!
ダムカードをもらおう!
豊平峡ダム資料室で令和5年11月2日までダムカードを配布中です。
平日 9:00~16:30 土日祝祭日は休館 おひとり様1枚限りです。
豊平峡では、支笏洞爺国立公園内にあるので自然環境保全を考え、豊平峡ダム入口から豊平峡園地までの約2kmは、自家用車で行くことはできません。
一般車両・バイク・自転車の乗り入れが通年禁止、電気バスを利用します。
豊平峡の紅葉は、北海道屈指の紅葉スポットです。
北海道は、秋になると急激に日中と朝晩の寒暖差が大きくなるのでより鮮やかな紅葉が見られます。
赤、黄色、オレンジとその中に一年中葉をつけたままの「常緑樹」の緑が加わり、そのバランスが見事です。
10月に入ると休日だけでなく平日にも、豊平峡駐車場が満車になることもあります。
定山渓観光案内所から豊平峡ダムまでのシャトルバス・豊平峡ダムライナーが運行されていますので便利ですね。
豊平峡公式サイトでは、駐車場の混雑状況や紅葉の色づき情報なども発信していますのでお出かけ前にチェックするといいですよ。豊平峡公式サイトはこちら
札幌市から定山渓温泉を通り豊平峡温泉までのバスがあります。
・じょうてつバスのカッパライナー号
・じょうてつバスの豊平峡温泉行路線バス(快速7J-H)
豊平峡温泉から豊平峡ダム入口までは、およそ3キロありますが、この区間は、バスがありませんので徒歩で行くしか方法がないです。
札幌市内から定山渓を通り豊平峡温泉まで運行されているカッパライナー号は、予約制です。
定山渓観光案内所から豊平峡ダムまでのシャトルバス・ダムライナーが秋期間運行されています。
全山紅に染まる紅葉。
豊平峡の燃えるように色づく紅葉をみてみたいですね。
紅葉を見た後は、豊平峡温泉や定山渓温泉で温まって帰ってはいかがでしょう。
定山渓には、ほかにも見どころがたくさんあります。
定山渓温泉・豊平峡温泉・定山渓ダムのまとめ記事は、こちらをご覧ください。

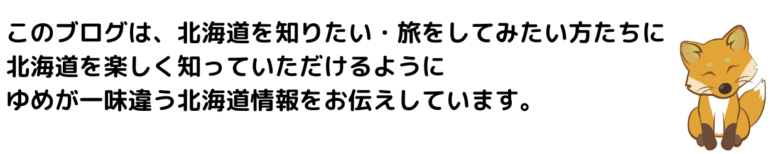







コメント
Hey! Someone in my Facebook group shared this website with us so I came to look it
over. I’m definitely loving the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to
my followers! Fantastic blog and excellent design.
Hello!Someone posted it on Facebook.
Thank you for bookmarking.
We will continue to provide information about Hokkaido, so please keep checking back.