
洞爺湖畔にそびえ褐色の山肌を見せている標高737メートルの有珠山(うすざん)は20世紀に入り4回も噴火している活火山です。
いまなお噴煙を上げる有珠山は、平成12年(2000年)から続いた噴火は、毎日のようにテレビで放映されたので記憶に残っている人も多いでしょう。
今回は、有珠山の今までの噴火の歴史と被害、今後の噴火の予測ができるのか?
などについてお話しします。
有珠山の歴史
有珠はアイヌ語でウㇲ(入江)という意味でございます。
この入江とは現在の伊達市有珠町の噴火湾沿岸の入り江のことを指しています。
では、有珠山の噴火の歴史を見てみましょう。
20世紀以前
有珠山ができたのは約1~2万年前の事です。
何度も噴火を繰り返し有珠山の元となる成層火山と溶岩ドームができました。
約16000年前には、山体崩壊が発生しました。
この山体崩壊で有珠山は現在の姿に近くなりました。
この時に南麓で火山泥流が発生してその後、低所が湾になりました。
これが有珠湾です。
溶岩の塊できた大小の小山が散在し湾口南側のポロノット岬、湾口のポロモシリ島・ポンモシリ島は防波堤の役割を果し、有珠湾は天然の良港となったのです。
有珠山の火山活動は、有史以降たびたびあり、確かな記録として残っているだけでも六回を数えています。
山体崩壊の後は、長い間噴火は全くありませんでした。
寛文3年(1663年)に突然地震が多くなり噴火活動が始まりました。
8月16日の明け方から山頂カルデラで流紋岩マグマによるマグマ水蒸気噴火がはじまりました。
この噴火は、大きな噴火で8月の末まで続き東北まで鳴動が伝わったとの記録があります。
20世紀に入ってから
20世紀には、明治43年(1910年)、昭和18年(1943年)、昭和52年(1977年)、平成12年(2000年)と4回も噴火をした活火山です。
その後大きな噴火を何回も繰り返しながら1910年、1943~45年、2000年の噴火ではマグマ水蒸気噴火や水蒸気噴火が発生しました。
噴火の度に大有珠、小有珠、おがり山、四十三山、昭和新山などの山々が新しくでき、洞爺湖温泉を観光地として発展させてきたのでございます。
有珠山噴火による被害
昭和52年(1977年)の噴火
「災害は忘れた頃にやってくる」と、有名な言葉がありますが、北海道随一の観光地を誇る洞爺湖畔にそびえる有珠山は、昭和52年(1977年)8月7日昭和新山の爆発以来32年ぶりに噴火し、その活火山としての健在ぶりを見せつけました。
前日は、昭和新山で花火大会があり何度となくある、有感地震に地元の人たちも昭和新山が噴火するんじゃないかと不安を募らせていましたが、噴火したのは有珠山でした。
この噴火では、噴煙は12,000メートルの高さまで達し、吹きあげられた噴煙は、遠く網走まで達し道内の半分近くの市町村を覆いました。
噴火終了後泥流災害も発生しました。
5階建ての町営住宅の1階部分が泥流で埋まり4階建てになったのには衝撃を受けました。
死者2名、行方不明者1名、軽傷者2名、住家被害196棟、非住家被害9棟、農林業・土木・水道施設等に大きな被害をだし、翌年の昭和53年(1982年)3月まで活動は続きました。

私は、昭和52年(1977年)8月7日の早朝6時まで洞爺湖にいました。
前日夜の昭和新山の花火を見るため、友達4人で昭和新山入り口の洞爺湖の湖畔でキャンプをしていました。
本当に地震が多く花火を見ながら、今にも昭和新山が噴火するんじゃないかと思ってちょっと気持ちの悪い感じがしました。
揺れと一緒に短い間隔で不気味な音が聞こえていました。
後で知ったのですが昭和新山ができた時にも同じような音がしたそうです。地震も揺れ方が激しいので地震で揺れているのか花火の振動なのか分からない感じでした。
地元の方も絶対噴火すると話していました。
地震はずっと続き全然寝れませんでした。
この日は仕事だったので友達を残し、6時に洞爺湖を出発ました。
住んでいた室蘭に一度帰り家で着替え千歳空港に向かいました。
登別のあたりから空が暗くなりました。
曇っているのとはまた違う暗さです。
車のウィンドウ に何か降ってきました。
火山灰です。
段々量が増えてワイパーがきかないくらいでした。
ラジオから9時12分有珠山が噴火したと聞こえてきました。
今朝見ていたばかりの有珠山です、怖いなぁと思いました。
後日友達が有珠山噴火の瞬間を写した写真を引き伸ばしてくれました。
写真を写してすぐに避難したそうです。
今考えると、私たちは怪我もなく何事もなかったから良かったですが、あんなに地震があったんですからキャンプはやめるべきでした。
平成12年(2000年)の噴火

一番最近の噴火は、平成12年(2000年)3月31日金毘羅さん山麓からマグマ水蒸気噴火が発生し火口周辺に噴石を降らせました。
火口は、洞爺湖温泉街のすぐ近くです。
噴煙は、高さ3500mまで達し千歳市でも微量の降灰がありました。
4月中旬まで、小規模な水蒸気噴火を繰り返し、西山西麓と金比羅山周辺に計65個の火口ができました
この噴火では、熱泥流が発生しました。
金毘羅火口から湯気を上げながら流れ出したのです。
4月中旬以降、活発な火口は4つに限定されましたが、西山西麓ではマグマにより最大約80m隆起してドームが形成されました。
小規模な噴火でしたが、道路や下水道が寸断されるなど850戸の家屋に被害がありました。
た。
ただこの噴火による死傷者はいませんでした。
2000年の噴火の様子です。
これでも、今までの噴火の中では一番小さな噴火だそうです。
有珠山噴火の予測
今なお続く火山活動、おおよそ20年から30年の周期で噴火を繰り返しています。
気象庁では、地震計、傾斜計、空振計、GNSS、監視カメラを設置し、常時火山活動の監視・観測を行っているのです。
これは、昭和52年(1977年)8月7日の噴火後、北海道大学の教授岡田 弘さんが中心となり有珠山麓に付属有珠火山観測所が作られました。
調べられたデーターと地震が増えてきていたことから近隣町民を事前に避難させたので2000年の噴火では、死傷者が出なかったのです。
岡田 弘さんは、この後20年間有珠火山観測所の所長として噴火予知研究に専念しました。
「有珠山はうそをつかない山」といわれているそうです。
噴火が近ずくと必ず地震が多くなったり、洞爺湖の水位が下がったりの地殻変動があります。
こちらのユーチューブは、今までの有珠山の噴火活動が詳しく説明されています。
興味のある方は、ご覧ください。
洞爺湖のおみやげ
洞爺湖のお土産は、こちらをご覧ください。


有珠山の噴火についてのまとめ
洞爺湖の湖畔にある有珠山の噴火の歴史。
噴火による被害。
今後の噴火についてお話ししました。
前の噴火から24年が経ちました。
20年から30年で噴火している有珠山ですから、いつ噴火しても対処できるように備えが必要ですね。
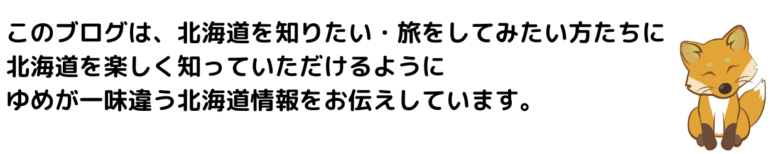



コメント